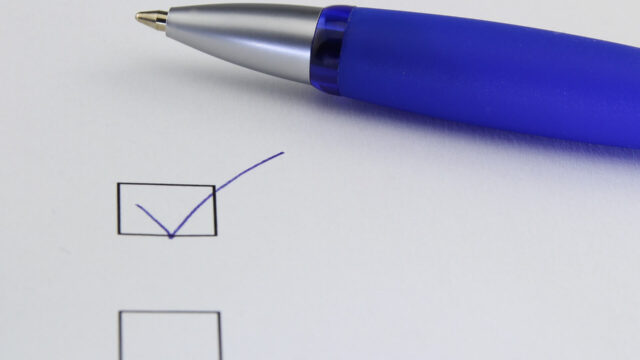初めに
ボルダリングを始めると誰もが思うこと。
『上手くなりたい』
『強くなりたい』
ボルダリングに夢中になる人の共通点として、負けず嫌いで向上心がある人が多い気がします。そんな時におすすめのトレーニングがサーキットトレーニングというものになります。
私自身ボルダリングを始めてしばらくの間は停滞期というものをほとんど感じることなく、ぐんぐん成長していきました。
その要因の1つとして考えられるのがこのサーキットトレーニングだったのです。
この記事を読めば、今後取り入れるべき『サーキットトレーニング』について理解し、実践できるようになります。ポイントを絞って簡潔に解説していきます。
①サーキットトレーニングとは?

サーキットトレーニングとは、過去に自分が登れた課題を一定数ピックアップして登るトレーニング方法になります。
人によっては『ツアー』と呼んでいる人もいます。
例えば、クライマーA君で考えてみます。
- 最高グレード:3級
- 【3級常設課題】15本中10本クリア
- 【4級常設課題】10本全てクリア
- 【5級常設課題】10本全てクリア
サーキットトレーニングは、登りたい課題をある程度トライし終わった後(全くヨレていない状態ではなく、身体が疲れてきた状態)で行うことでより効果を感じることができます。
②やり方と意識するポイント

この場合、A君は残り5本の3級の課題をなんとかして登れるようになりたい状況です。
サーキットトレーニングは、
まずどの課題をサーキットするか決めるところから始まります。
A君におすすめの課題選びは以下のようになります。(自分の限界グレードを中心に少しぐグレードを下げて課題を選ぶ)
- 5級と4級の課題20本をサーキット【持久力】
- とにかく登り切る意識(どんなにヨレていても)
- 4級全てをノーミスでサーキット【集中力】
- ノーミスで全課題を登る意識
- 3級の登れている課題10本をサーキット【底上げ】
- 3トライ以内で登る意識
- 最高グレードでもあるため再登できなくてもOK
- いつかはこのサーキットをやり切るという意識は持っておく
意識してほしいポイントは、ただ登るだけではなく何か1つでも自分ルールを決めてそれをやり切るサーキットにする事です。
少し難しく感じるかもしれませんが、それぞれのサーキットの目的を決めてサーキットトレーニングを行なってほしいのです。
意識するポイントは細かなものでもOKです。
- 極力レストはしない
- ホールドを1つ飛ばしてみる
- とにかく丁寧に登る
- 絶対に足を切らない
- ロックしながら登る
- 親指を使わない
など。
③メリット

サーキットトレーニングのメリットには以下の点が挙げられます。
- 持久力がつく
- ムーブが体に染み込む
- 登りが綺麗になる
- 集中力がつく
- 粘り強さがつく
普段よりトライする課題の数が増えるので、持久力アップにつながります。
また1度登れたことがある課題を再登することになるので、繰り返すことでムーブが自動化かされ無駄な動きが削ぎ落とされ、自然と脱力した綺麗な登り方に近づきます。
トライ数の意識を組み込むと、ヨレた状態で登り切るための集中力アップや粘り強いクライミング力も付きます。
私が行なっていたルーティンは、
- ストレッチ
- アップ
- 限界グレードの出来そうな課題にチャレンジ
- ヨレてきたらサーキットトレーニグ
登る日と決めた日は基本的に上記のルーティンでトレーニングしていました。
④デメリット

- 時間がかかる
- 混んでいるとやりにくい
ぐらいでしょうか。
トライする課題数が増えるので当然、かかる時間も増えてしまいます。
仕事終わりになんとか時間を捻出して登っているクライマーには難しい面もあります。
私も大学生から社会人クライマーになった時は、かなり苦労しました。
また、ぐるぐるとジム中のいろんな壁の課題をトライすることになるので、混んでいる時間帯などはトライするタイミングが難しく少しやりづらいかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
サーキットトレーニングは1人でやると想像以上に退屈に感じてしまうかもしれません。
同じグレード感の人を誘ってやってみるのもおすすめです。
セッション相手とルールを決めてやるのもいいでしょう。
今日から早速サーキットトレーニングを取り入れてレベルアップしていきましょう!
次回の記事もお楽しみに♪